【保存版】夫が病気で働けなくなり「ひとり親認定」されたときに使えた支援制度まとめ|児童扶養手当・医療費助成・学童費用の減免まで実体験で解説
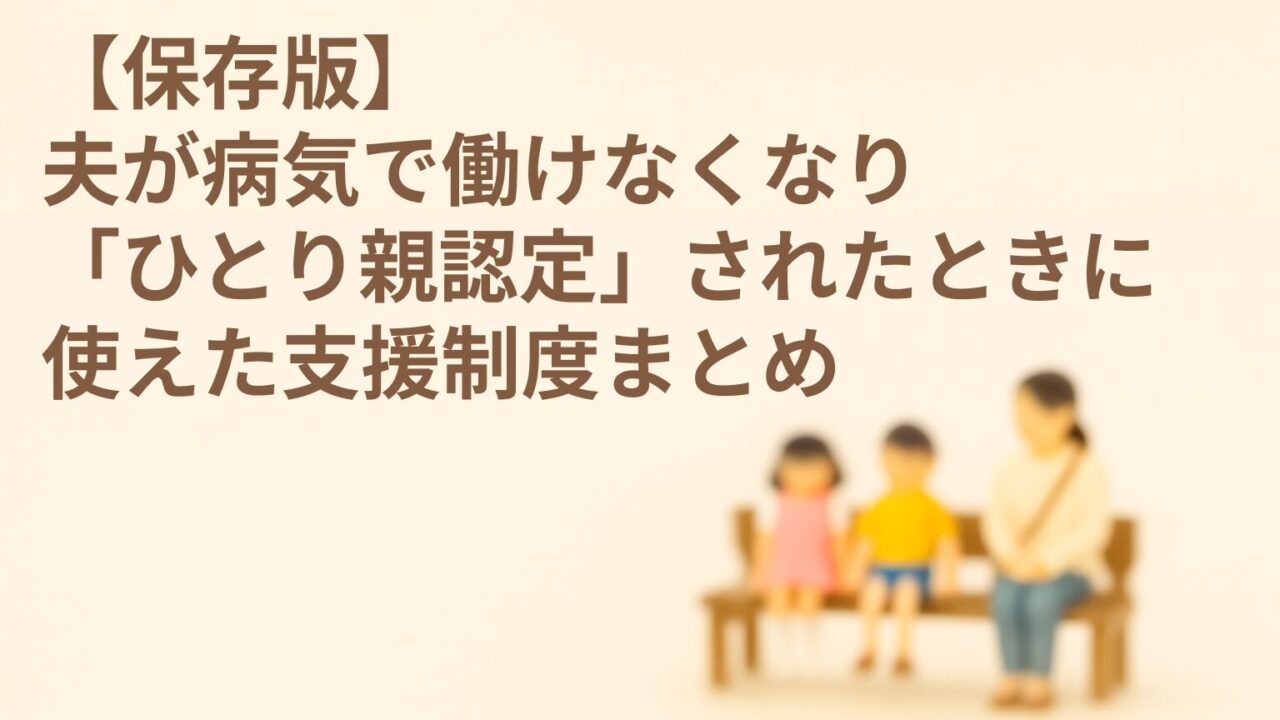
離婚はしていないものの、家計を主に支えていた夫が病気で働けなくなり、私は子どもを育てながら一家の生活を維持する立場になりました。そこで市役所へ相談し、ひとり親認定を受けたことで次のような制度を活用できています。
- 児童扶養手当(現在は一部支給)
- ひとり親家庭等医療費助成(医療費の自己負担軽減)
- 学童クラブ利用料の減免
- 塾代助成制度
この記事では、実際に助けられた順に制度を紹介し、申請のコツや注意点をまとめました。これから手続きを考えている方の参考になれば幸いです。
離婚していなくてもひとり親認定を受けられることがある
離婚していなくても、ひとり親認定を受けられることがあります
「ひとり親」と聞くと、離婚や死別を思い浮かべる方が多いかもしれません。
ですが、実際には、配偶者が重度の障害を負い働けない場合も対象になることがあります。
私自身、夫が病気の後遺症で働けなくなり、身体障害者手帳1級を取得したことがきっかけで、「ひとり親認定」を受けることができました。
市役所で児童扶養手当について相談した際、「配偶者が重度障害でも要件に該当する可能性がある」と教えていただき、正式に申請を行いました。
自治体のガイドラインには、「配偶者が政令で定める重度障害に該当し、長期療養で働けない場合」も対象となると明記されていることがあります。
このように、配偶者が働けない、別居している、生活費の支援を受けていないなど、家庭の状況によっては、離婚していなくても支援の対象になる場合があります。
認定の可否は、世帯の状況や所得などを総合的に判断して決まるため、まずは相談窓口で事情を説明し、必要な書類や手順を確認することが大切です。
「相談するだけでも情報が得られ、支援への第一歩につながる」ことを、私自身が実感しています。
もし迷っているなら、まずは一度、窓口へ足を運んでみてください。
参考記事:ひとり親認定で使えるようになった制度
児童扶養手当が 「ひとり親認定」への入り口になった体験
「何から手を付ければいいのだろう」と手続きに迷った私は、まず 児童扶養手当 の申請に挑戦しました。そろえる書類は多かったものの、戸籍謄本や所得証明、夫の障害年金証書(子の加算が分かる部分まで)など、家族の状況を示す資料を一度に用意したことで、自分が置かれている環境を役所側にも具体的に伝えられたと感じています。
児童扶養手当は、「申請すればすぐにもらえる」というものではなく、以下のような流れで進んでいきます。
【相談・情報収集】→【申請書類の準備】→【申請書類の提出】→【審査】→【支給開始】
具体的には、自治体の窓口で必要書類を提出したあと、家庭の状況や所得などをもとに審査が行われ、要件を満たしていれば「認定通知書」が届きます。その後、認定された翌月分から手当の支給が始まるのが一般的です。
ただし、認定までは1か月以上かかることもあり、申請が遅れると支給も後ろ倒しになります。支給は年に3回(4月・8月・12月など)にまとめて振り込まれる方式が多いため、できるだけ早めの申請を意識することが大切です。
わが家では、審査を経て一部支給が決定したあと、窓口の方から「こちらの制度も利用できますよ」といった案内を受けることができました。児童扶養手当の申請をきっかけにやりとりが増え、ひとり親として利用できる支援制度が自然と見えてきたというのが正直な実感です。
利用できるサポートを早めに把握しやすくなると感じました。
書類をそろえるときに心がけたこと
✔ チェックリストで抜け漏れを防ぐ
窓口で受け取ったリストに沿って、一つずつ確実に用意しました。見落としがないよう、チェックしながら進めることで安心感がありました。
✔ 疑問は電話で確認してから提出
足りない書類がないか事前に電話で確認しました。そのおかげで再来庁の手間が省け、スムーズに申請が進みました。
書類の山に圧倒されそうになりましたが、「これも将来の安心につながる一歩」と考えて進めるうちに、制度への距離がぐっと縮まったように感じました。
毎年8月は「現況届」の提出月|忘れずに手続きの準備を
児童扶養手当を受け取り続けるには、毎年8月に「現況届」 を提出する必要があります。私の住む市では、7月下旬に書類が郵送で届きました。その中に、受給者番号ごとに市役所へ訪問する日程が振り分けられている案内も同封されており、窓口の混雑を防ぐ工夫がされています。
現況届を提出しないと、11月以降の支給が止まってしまうため、手続きを忘れないように注意が必要です。
今後は書類の内容をよく確認し、必要な持ち物や提出期限を早めにチェックしておく予定です。
ということにならないよう、早めの準備を心がけています。
ひとり親家庭等医療費助成制度|保護者も対象になる支援内容とは
「子どもの医療費が助成される制度」はよく知られていますが、じつは条件によっては保護者自身も対象になる場合があります。私自身、この制度のおかげで安心して医療機関を受診することができています。
病気や障がいのある配偶者を支えながら、子どもを育てる生活は、体力的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。そんな中、医療費の不安が軽減されるだけでも、心の余裕が生まれました。
医療費助成で保護者も支援対象に|実体験からわかったこと
医療費助成制度の対象となるのは、以下のような家庭です。
- 母子家庭または父子家庭の保護者と子ども
- 配偶者が一定の障がいの状態にある保護者と子ども
- 養育者と、父母のいない子ども
ここでいう「子ども」とは、18歳に達した年度末(3月31日)までの間にある方を指します。
私の家庭では、夫が病気で重度の障がいを負い、働くことが難しくなりました。役所で相談したところ、この条件に該当し、子どもだけでなく私自身も助成の対象になると案内されました。
病気の夫と子どもを抱える生活の中で、もし自分が体調を崩してしまったらどうしようという不安はずっとありました。医療費の負担が少なくなったことで、体調に不安を感じたときも、ためらわずに受診できるようになりました。それが、日々の安心につながっています。
医療費助成の内容と仕組み|外来・入院で異なるサポートがあります
ひとり親家庭等医療費助成制度では、外来と入院で自己負担の上限額がそれぞれ設定されています。経済的な不安が軽くなることで、体調が心配なときも早めに受診するきっかけになりました。
外来の場合
同じ月に同じ医療機関を受診した場合、1人あたりの自己負担は1,000円までと決まっています。たとえば、子どもが風邪で2回通院したとしても、合計の支払いは1,000円以内で済みました。
※食事療養費や一部対象外の費用は含まれません。
入院の場合
入院時の自己負担についても、保険診療のうち食事療養費を除いた部分が助成の対象になります。長期入院となった場合も、助成のおかげで家計への影響を抑えることができました。
※助成内容や上限金額は、市町村ごとに異なります。お住まいの地域の制度をご確認ください。
医療費助成が使えないケースとは?対象外になる条件と注意点
助成が受けられないケースもあります。たとえば、以下のような場合は対象外となります。
- 学校や保育園など施設の管理下でのケガ(災害共済給付制度が適用されるため)
- 仕事中のケガや通勤災害など、労災の対象となる医療費
- 第三者から賠償される予定の医療費(交通事故など)
- 高額療養費や健康保険組合からの付加給付金がある場合、その部分は助成の対象から除かれます
医療費助成の内容は自治体によって違う?確認ポイントまとめ
この医療費助成制度は、市区町村によって内容に違いがあります。たとえば、以下のような点は自治体ごとに異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
- 対象者の条件(例:保護者本人も助成対象になるかどうか)
- 助成される医療の範囲(外来・入院・薬局など)
- 自己負担額の割合や上限額
- 対象となる医療機関や薬局の指定有無
- 助成を受ける際に必要な手続きや受給証の提示方法
こうした内容は、申請時に窓口で丁寧に説明してもらえることが多いですが、不明点は受診前でも気軽に相談しておくと、制度を無理なく活用しやすくなります。
学童クラブの費用が減免された
児童扶養手当の受給証で学童費用が軽くなる
ひとり親認定を受けて児童扶養手当の受給証をもらったあと、学童クラブに提出することで「利用料の減免制度」が使えるようになりました。
わが家では、毎月かかっていた学童の費用が減額され、家計の負担が軽くなりました。
学童の減免制度は「入所」が前提
制度の存在を知ったのは、児童扶養手当の受給が決定した11月のことでした。
すでに学童クラブの定員はいっぱいでしたが、それでも諦めずに「せめて名簿だけでも入れてください」とお願いし、施設に直接足を運びました。
結果として、翌年4月から下の子だけでも入所が決まりました。
実は、学童利用料の減免制度は「学童に入所していること」に加えて、「児童扶養手当を受給していること」も前提条件となっていました。
制度を利用したくても、手当の受給がなければ対象外になってしまいますし、そもそも学童に入れなければ減免は受けられません。
※この減免制度は、あくまで「学童に入所しており、児童扶養手当を受給していること」が前提です。申し込みが遅れた場合、制度の対象そのものになれないこともあるため、入所手続きや手当申請は早めに動くことをおすすめします。
制度を知ってすぐに行動したことで入所につながり、結果的に減免も受けられるようになりました。
早めの相談と申請が本当に大切だと実感しました。
減免の手続きと返金の流れ
学童クラブに、必要書類とあわせて児童扶養手当受給者証のコピーを提出しました。
減免が認められたのは入所から2か月ほど経った頃で、それまでに支払った月謝の一部が返金されました。
実は、季節外れの入所をお願いするだけでも気が引けていたため、「減免の相談まではしづらいな…」と感じていました。
それでも思い切って伝えたところ、先生方は快く受け止めてくださり、申請の流れも丁寧に案内してくれました。
今でも、あのとき温かく迎えてくださったことに感謝しています。
参考記事:学童クラブの費用が軽くなった話
【体験談】塾代助成制度でタブレット学習を継続|申し込み方法と注意点も紹介
※利用には制限や注意点もあるため、実際の体験をもとにまとめました。
子どもの学びを支えるために、わが家では自治体の「塾代助成制度」を活用させていただいています。現在小学生の子どもは、タブレット教材を使って毎日在宅での学習を続けています。
この制度では受講料の一部が補助されるため、家計の負担を抑えながら教育機会を維持することができています。通学型の塾だけでなく、オンライン学習にも対応しているため、子どもが希望したオンラインコースを選択しました。
対象となる学習サービスには、たとえば公文式や学研のような有名な塾、さらには英語教室やプログラミングスクールなども含まれていて、幅広い選択肢から子どもに合った学び方を選べるのも魅力のひとつです。
利用にあたっては、希望する塾に事前に連絡を取り、自治体の案内に沿って手続きを進めました。年払いのタブレット学習コースを選んだため、助成金だけでは全額をまかなうことはできませんでしたが、差額を自己負担して、無理なく学習を続けられています。
利用する際の注意点
1. 利用できる学習塾・教材には制限がある
すべての塾やオンライン教材が助成対象になるわけではありません。自治体が指定した対象施設のみで、登録されていない場合は助成を受けられないため、事前に塾側と確認しておくことが大切です。
2. 申し込み前に「利用承諾書」の提出が必要なことも
多くの自治体では、利用予定の塾から「利用承諾書」や「証明書」を発行してもらい、自治体に提出する流れがあります。事後申請は受け付けてもらえないケースもあるため、申し込み手順は事前にしっかり確認しましょう。
3. 年払いコースは差額が大きくなる場合がある
わが家でもそうでしたが、年払いコースを選ぶと助成金の範囲を超えることがあるため、自己負担分がどのくらいになるかをあらかじめ計算しておくと安心です。
4. 助成期間や上限額に注意する
自治体によって助成の**対象期間(月ごと/年度ごと)や支給上限額(月額1万円など)**が異なります。対象期間外や超過分は全額自己負担になるため、利用前に制度概要をチェックしておきましょう。
5. 対象者の条件もある(所得制限・学年制限)
助成を受けられるのはひとり親家庭や非課税世帯などの条件が設定されていることが多いです。また、学年の上限(例:中学3年生まで)がある自治体もあります。
塾代助成制度は、家庭の経済状況にかかわらず、子どもが安心して学べる環境を支えてくれる大切な仕組みです。
わが家では、オンライン教材の受講にこの制度を活用することで、勉強の習慣を無理なく続けることができました。利用には事前確認や手続きが必要ですが、「子どもの学びたい気持ち」を応援できる仕組みがあることに、私自身とても救われています。
制度の利用を検討している方は、まずお住まいの自治体のホームページや窓口で、対象条件や手続き方法を確認してみてください。「知らなかった」で終わらせるにはもったいない、頼れる制度のひとつです。
【一覧表あり】ひとり親家庭で使える6つの支援制度まとめ
ここまでに紹介した制度に加えて、実際にわが家が利用したもの、これから申請予定の制度も含めて、ひとり親家庭が活用しやすい支援制度をまとめました。
「申請先がわからない」「どれから始めればいいのか迷う」という方も、まずは全体像を確認して、自分に合う制度をチェックしてみてください。
| 制度名 | メリット | 申請先 | 申請の流れ・備考 |
|---|---|---|---|
| 児童扶養手当 | 子どもの人数に応じた手当がもらえる | 市区町村(子育て支援課) | 所得・戸籍などの書類を提出→審査後に支給開始(年6回) |
| ひとり親家庭医療費助成制度 | 医療費の自己負担が軽減される | 市区町村(子育て支援課) | 児童扶養手当と連動/別途申請で医療証発行される |
| 学童クラブ利用料減免 | 放課後保育の費用が減額または無料になる | 学童クラブ or (子育て支援課) | 認定証(例:児童扶養手当証書)などを提示して申請 |
| 塾代助成制度 | 学習塾・オンライン教材に利用できるクーポンがもらえる | 市区町村(こども政策課) | 対象塾での登録→制度サイト経由でクーポン申請 |
| 自立支援教育訓練給付金 | 働くための資格取得に使える(最大20万円) | 市区町村(自立支援担当) | 対象講座か確認→事前相談→講座修了後に給付金申請 |
| 高等職業訓練促進給付金 | 月額10万円以上の給付で資格取得を支援 | 市区町村 (子育て支援課) | 対象資格か確認→事前相談→訓練中も定期提出あり |
制度によって対象条件や申請方法が異なるため、気になる制度があれば自治体の窓口や公式サイトで早めに確認してみてくださいね。
ひとり親が受けられる制度① ─ 自立支援教育訓練給付金
ひとり親が就職や転職につながる資格取得を目指す場合に活用できるのが、自立支援教育訓練給付金です。この制度を利用すると、対象講座の受講料の6割(上限20万円)を国と自治体が補助してくれます。
ひとり親が就職や転職につながる講座を受ける場合、受講料の 6 割(上限 20 万円) を国と自治体が補助してくれます。医療事務や簿記、介護・保育関係など、求人が安定している資格が対象です。
- 医療事務、簿記、パソコンスキル
- 介護職員初任者研修、保育士
- 調理師、歯科衛生士など
制度を活用したい場合は、ハローワークや市区町村の窓口で講座の内容や支給対象かどうかを事前に確認することをおすすめします。
✅ 対象となる講座は、厚生労働省の教育訓練給付制度講座検索システムで調べることができます。講座名・分野・地域などから検索でき、受給対象かどうかを事前にチェックできます。
ひとり親が受けられる制度② ─ 高等職業訓練促進給付金
ひとり親が1年以上の専門的な資格取得に挑戦する場合に頼りになるのが、高等職業訓練促進給付金です。
この制度を利用すると、養成校や専門学校などに通っている間、生活費の一部を支援してもらえます。資格取得中は働ける時間が減るため、家計の支えとなる制度です。
給付の内容
- 支給期間:最長4年間
- 支給額の目安(月額)
- 市町村民税非課税世帯:10万円前後
- 課税世帯:7万5千円前後
- 卒業年の最後の12か月間は、さらに上乗せ支給される場合があります
※金額や支給期間は自治体によって異なるため、必ず最新情報を確認してください。
対象となる資格の例
- 看護師・准看護師
- 保育士
- 理学療法士・作業療法士
- 社会福祉士・介護福祉士 など
専門学校・短大・大学での就学が前提となる資格が対象です。
利用の流れと注意点
この制度は、就学前に申請が必要です。
制度を利用したくても、入学後に申請しようとしても対象外になる場合があるため注意が必要です。 早めに市区町村の窓口で相談し、必要書類やスケジュールを確認しておくと安心です。
✅この制度の対象講座についても、厚生労働省の講座検索システムで確認できます。
制度を活用するには「自分から調べて動く」ことが大事
多くの制度は、申請しないと使えません。
さらに言えば、制度の存在そのものを知らなければ、申請のきっかけさえつかめません。
私も市役所に何度も足を運び、窓口で相談しながら情報を集めました。
インターネットでは得られない情報を、窓口では丁寧に教えてくれることも多かったです。
その一歩が、支援につながる道でした。
まとめ|ひとり親認定はゴールではなく、支援制度を知るきっかけに
「ひとり親認定を受けたから支援が自動的に始まる」というわけではありません。実際に制度を活用するためには、自分から申請したり、条件を満たしているか確認したりと、行動が必要でした。
とはいえ、認定をきっかけに制度の存在を知り、必要なサポートにたどりつけるようになったのも事実です。
わたし自身、医療費助成や塾代助成、学童費用の減免など、子どもを育てながらの生活を支えるさまざまな制度に助けられてきました。
これから申請を考えている方、制度について調べている方が、この記事を通じて少しでも安心できたり、次の一歩を踏み出せたりしたらうれしいです。



