【急性期・一般病棟での体験談】夫が心筋梗塞で倒れ、意識が戻ってから始まった新たな不安と希望

※こちらは後編の記事です。
前編はこちら▶︎【急性期・ICU体験談】夫が心筋梗塞で倒れた日と、家族が意識不明の中でできた3つのこと
ICUでの治療を終え、夫が一般病棟へ移ったとき――
ようやく意識が戻り、「これからは回復に向かうだけ」と信じた瞬間でもありました。
けれど実際に始まったのは、想像と異なる現実と、新たな壁への挑戦でした。
面会制限のなか、私たち家族にできたことは限られていましたが、
オンライン面会で声をかけ続け、相談員さんと連携しながら受け入れ先を探し、
リハビリ職の方と情報をつなぎながら、少しずつ前へ進んでいきました。
この記事では、一般病棟でのリハビリの様子や胃ろう造設の判断、
そして回復期病棟への転院に向けた葛藤など――
意識が戻ってから始まった不安と、それでも見えてきた小さな希望についてまとめています。
意識は戻った──でも首を上げられない現実

「ご主人が目を開けました」と ICU から知らせを受けた瞬間、胸が熱くなりました。
ところが一般病棟でオンライン面会をつないでみると、画面に映った夫は確かに目を開けているものの首がだらりと垂れたまま。理学療法士さんが支えても、わずかな時間しか姿勢を保てません。思わず──
「夫が自分の力で首を動かすことはできないのですか?」
と尋ねてしまったほどです。
振り返れば、ICU では意識が戻る前の 3〜4 日目から立位訓練が始まり、大柄な夫を 4〜5 人がかりで支えてくださっていました。筋トレ好きで体幹の強い人だったので「きっと回復も早いはず」と期待しましたが、現実は想像よりずっと険しい道のりでした。画面越しの喜びは、すぐに重たい現実へと変わっていきました。
その後のリハビリで、うなずきや首振りが少しずつできるようになり、夫の「はい」「いいえ」が首の動きで読み取れるまでに回復しました。いま当たり前に感じる動きも、実は並々ならぬ努力の賜物だと痛感しています。
オンライン面会で見えなかった「手足の拘縮」

一般病棟では面会予約が取れず、タブレット越しのオンライン面会が中心でした。
画面に映るのは顔だけ。体全体の様子までは確認できません。
ある日、担当看護師さんから
「手足が少し固くなってきています」と告げられて、胸がざわつきました。
「もっと早く気づいていれば、何かできたかもしれない」
――そう思いながら、慌ててネットで拘縮予防用のクッションやグリップを購入し、リハビリスタッフに託しました。けれど、握ったままになりやすく効果は限定的だったようです。
子どもたちは画面越しに「パパ、がんばって!」と声を届け、夫が目を開けている日は積極的に話しかけました。しかし直接面会できない間に、手足は徐々に固まっていったのです。もし面会制限がなければ、もっとさするなどの刺激を与え、拘縮が進む前に気づいてあげられたかもしれません。
コロナ下での面会制限は仕方のないこと――それでも、あの日感じた悔しさは今も忘れられません。
家族の声かけと、わずかでも進んだリハビリの一歩
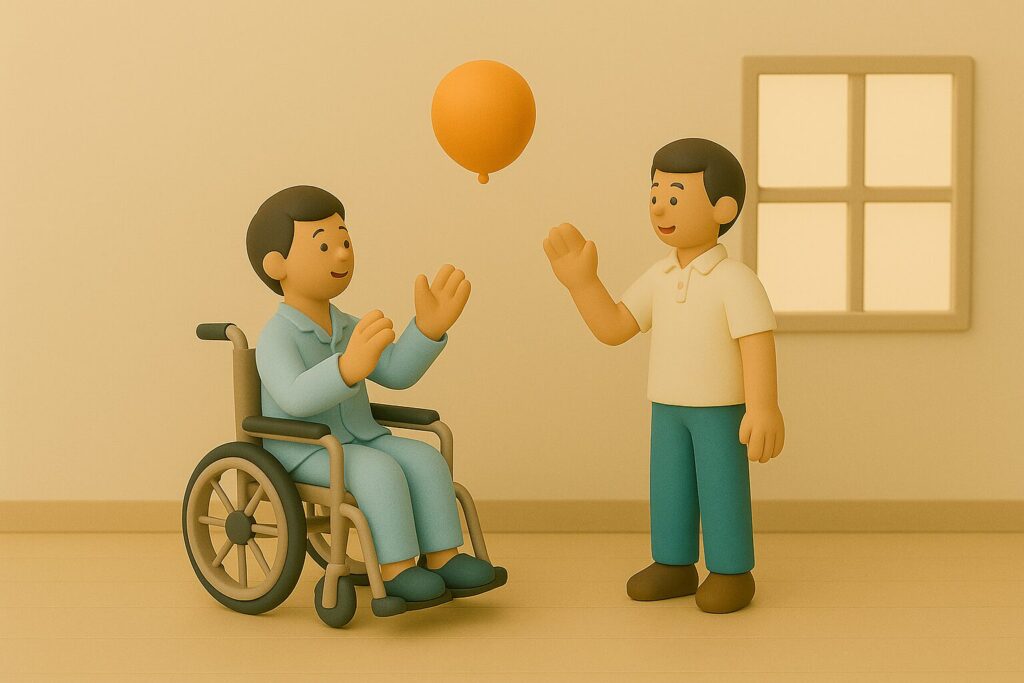
一般病棟では、理学療法士・作業療法士のチームが中心となり、夫に合わせたリハビリが始まりました。
食事もゼリー食に進み、経鼻チューブを一時的に外せるまでに。
なかでも印象的だったのが 風船バレー。
理学療法士さんがタブレットでその様子を録画し、私たち家族に見せてくれました。
画面には、風船をしっかり追いかけ、上手に打ち返す夫の姿――。
動画を見た子どもたちは「パパ、すごい!」「がんばってる!」と大はしゃぎ。
その声をオンライン面会で届けると、夫はベッドの上で両足をバタバタと動かし、全身で応えてくれました。
直接触れ合えなくても、声は確かに届き、励みになる──その瞬間を実感した出来事です。
その後、10日間だけ転院した関連病院でもリハビリを継続。
家族面会が許されない中、移動の車いすでヘッドホンを付け、夫の大好きな音楽を流して送り出しました。
「パパ、リハビリ頑張ってきてね!」
出発前の声かけに、夫はまた両足を力強く動かして応えてくれたのです。
わずかな時間、わずかな距離でも、家族の声とリハビリの一歩が確かに“前進”へつながったと感じています。
胃ろう造設に迷いながらも選んだ“前へ進む”選択
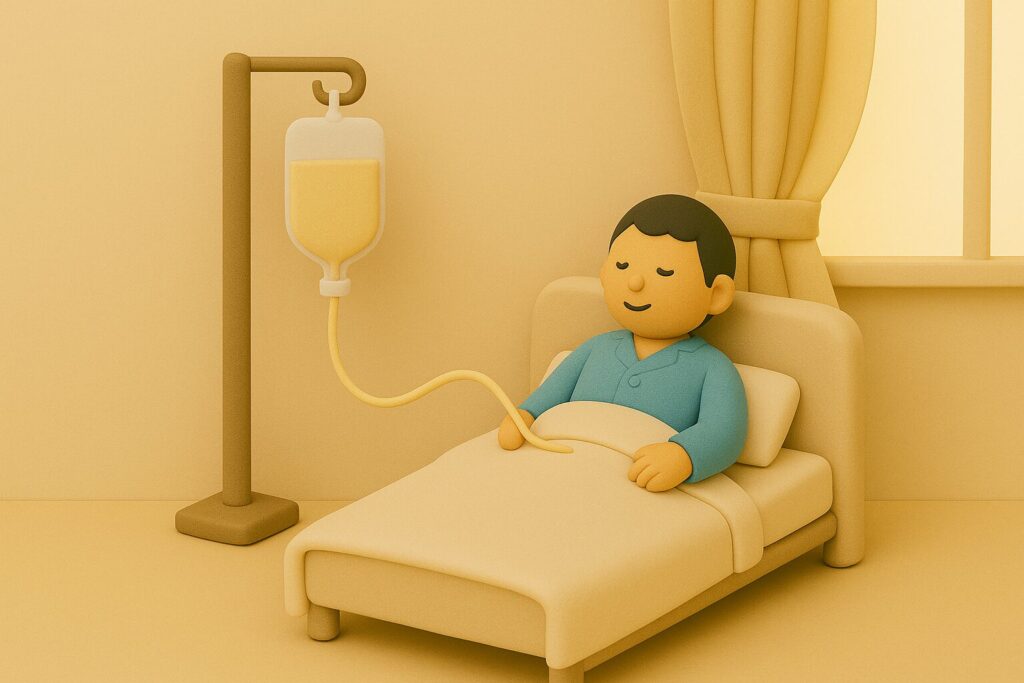
本当は経鼻チューブのままリハビリに進ませたかったです。
ところが主治医からは「回復期のリハビリ病院では経鼻栄養のままでは受け入れが難しい」と告げられ、胃ろう造設を強く勧められました。
手術日まで決まっており、「その日までに回避できないか」と何度も願いましたが、2週間ごとのチューブ交換が必要な経鼻では、医療体制が整った病院でなければ十分なリハビリが受けられないのが現実でした。
決断を遅らせていた理由は、口からチューブがなくなるメリットと手術リスクを天秤にかけても、夫本人の意思を確かめられないもどかしさがあったからです。
しかも ICU の主治医は「胃ろう=施設行き」という考えが強く、気管切開も積極的に勧めるタイプの先生でした。私の施設への直行ではなく、回復期病棟で集中的にリハビリさせたいという私の希望とは相容れませんでした。
それでも最終的には、「食べる・話す」訓練が広がることを信じて胃ろう造設を決断しました。手術後、経鼻チューブが外れた夫の表情はみるみる明るくなり、子どもたちの声に笑顔で応えるまでに意識がはっきりしてきました。24時間鼻にチューブが入っていた苦痛がなくなったことは、想像以上に大きかったのだと思います。
結果として、胃ろうにしたことで回復期病棟の受け入れ先も見つかり、「前に進む条件」を整えられたと今では確信しています。
リハビリ病院が見つからない焦りと 、介護保険の早期申請の後悔

胃ろうを造設すればすぐに回復期リハビリ病院へ転院できる――そう信じていました。ところが現実は甘くなく、「病状が重過ぎて受け入れが難しい」と各病院から立て続けに断られ、焦りだけが募っていきました。
そんなとき、相談員さんから勧められたのが介護保険の申請です。早く転院先を見つけたい一心で手続きを進め、病室で行われた市役所の訪問調査の結果、要介護4と判定されました。
ところが後になって愕然としました。実は64歳までは障害福祉サービスでも介護保険と同等の支援が受けられたのに、先に介護保険を取得したことでそちらの対象外になってしまったのです。障害福祉のサービスにしかないものは受けられるようですが、介護保険優先になってしまったのです。
「申請のタイミングをもっと調べていれば……」
転院先が決まらない焦りの中での早急な決断だったとはいえ、今も悔やまれる選択となってしまいました。
家族にできることは少なくても、確かに力になった

一般病棟に移ると、予想以上に家族が直接できることは限られていました。
それでも、私たちは “今できる小さなこと” を積み重ねるよう心がけました。
- オンライン面会で毎日声を届ける
- 担当看護師さんとこまめに連絡を取り、体調を確認する
- リハビリ職の方に進捗を共有してもらう
- 必要な物品を用意して、病棟へ託す
たとえばある日、オンライン面談のタブレット画面越しに、夫の鼻毛が伸びすぎて呼吸が苦しそうに見えました。
看護師さんに「入院中の患者さんはお手入れをどうされていますか?」と尋ねると、
「特別なケアはしていません」との返答。――背筋が寒くなりました。
直接病室へ入れないからこそ、こちらから動くしかない。
そこで電動式とハサミ式の鼻毛カッターを購入し、「使いやすい方でお願いします」と看護師さんに託したところ、
「呼吸が楽になったようです」と報告をいただけました。
質問してみる、気づいたことをお願いベースで伝える。
たとえ些細なことでも、家族が動けば環境を改善できる――その手応えを強く感じた出来事でした。
ようやく見つかった回復期病棟への道

胃ろう造設からおよそ 2 か月──。
「近くのリハビリ病院が受け入れてくれることになりました」と相談員さんから連絡が届いた瞬間、思わず飛び上がりそうになるほど嬉しかったのを覚えています。不安ばかりがふくらんでいた毎日に、ようやく光が差し込みました。
この頃には手足の拘縮が進んでしまっていましたが、それでも「これで前に進める」と家族全員で胸をなで下ろしました。
回復期リハビリが始まれば、きっと日常を取り戻せる――そんな希望が、再び力強く湧き上がったスタートラインでした。
まとめ|想定外を越えて、ようやく回復期のスタートラインへ

夫は意識が戻ったからといって、すぐに元の生活に戻れるわけではありませんでした。
私たち家族が直面したのは、一般病棟での新たな不安と現実。
拘縮の進行、胃ろうの判断、受け入れ病院探しと、次から次へと乗り越える壁が現れました。
それでも、家族の声かけ、医療スタッフとの連携、少しずつ積み重ねた情報ややりとりの中に、小さな光が見えてきました。
この記事が、いま急性期病院で大切な人を見守っている方、「意識が戻ったあと、どんな経過をたどるのだろう」と不安を抱える方へ、少しでもヒントや支えになれば幸いです。





