在宅介護で直面した4つのトラブルと備えのヒント|災害・停電・断水など現実の課題とは

在宅介護は、日常の暮らしの中に突然起こるトラブルと隣り合わせです。
我が家でも「断水」や「停電」、「エレベーター停止」など、予想もしていなかった場面で困ったことが何度もありました。
とくに、要介護の家族と一緒に暮らしていると、「もし災害が起きたら、どうやって避難するの?」という不安が常につきまといます。
この記事では、そんな私自身の体験をもとに「在宅介護で直面した4つのトラブル」と「そのときの備え」をご紹介します。
介護中の方や、これから備えておきたいと考えている方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。
断水で在宅介護がストップ|訪問サービスの日は特に要注意

マンションに住んでいると、年に数回、設備点検などで断水が行われることがあります。
普段の生活でも「ちょっと不便だな」と感じるものですが、在宅介護中となると話は別です。
手洗いや清拭、処置などに水が使えないと、いつもの介護が思うようにできず、焦りや不安が重なることもあります。
マンション断水の通知は要チェック
ある日、マンションの掲示板に「断水のお知らせ」が貼られていました。断水は約1ヶ月後とのことで、最初は「まだ先の話」とあまり気にしていなかったのですが、よく見るとなんと2日間続けて、1日あたり6時間以上の断水。しかも、その時間帯にちょうど訪問診療と訪問介護の予定が入っていたのです。
「えっ、この状態でどうやってケアするの…?」と不安になりました。
手洗いができなければ感染予防にも影響しますし、清拭に使うお湯や、処置後の片づけにも水は不可欠です。慌ててペットボトルの水を買いに行ったものの、まとめ買いした水を持ち帰るのはかなりの重労働で、エレベーターを使っての運搬も大変でした。
あのとき、「水がないだけで、こんなにも介護が不自由になるのか」と痛感しました。
ペットボトル・浴槽で「水の備蓄」を意識|断水への備えが介護を支える
それ以来、断水のお知らせを見かけたら、できるだけ早めに準備するように心がけています。具体的には、
- ペットボトルの水を数本多めにストック
- 浴槽に水をためておく(トイレや雑用水としても活用)
- 洗面器やバケツに水をためておく
- 断水時間の前後に訪問サービスの変更ができないか相談
といった、ちょっとした備えを意識するようになりました。
普段は何気なく使っている水が、在宅介護では本当に大切なライフラインのひとつです。
あらためて「水のありがたさ」と「早めの対応の大切さ」を感じた出来事でした。
エレベーター停止が不安を呼ぶ|高層階での介護スケジュール調整の工夫
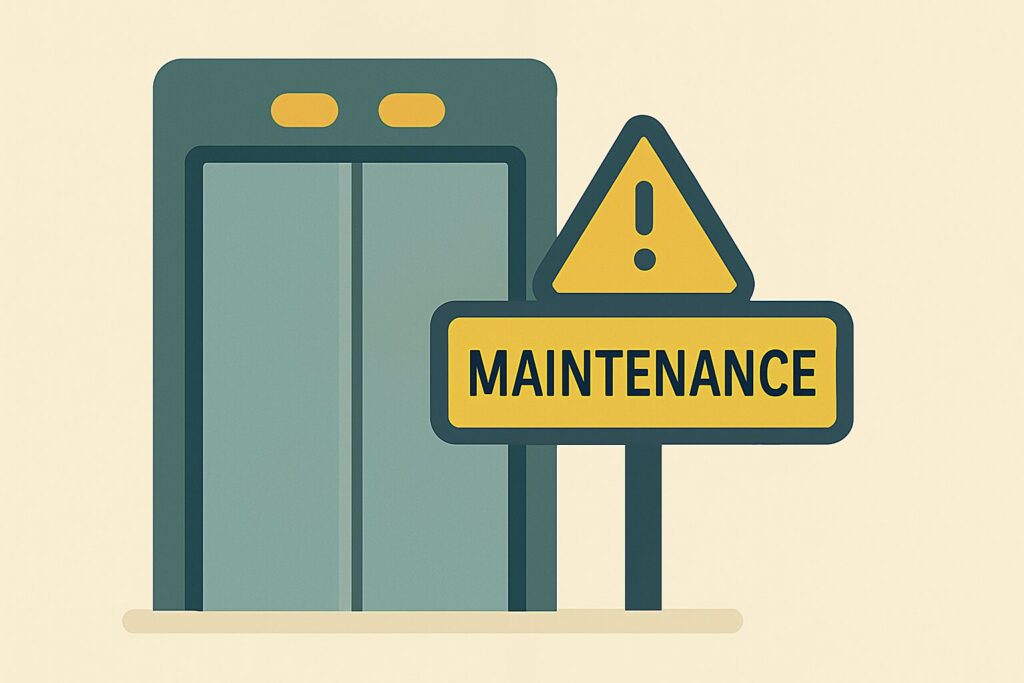
車椅子を利用している方にとって、エレベーターは毎日の生活に欠かせない存在です。
そのエレベーターが使えなくなるだけで、在宅介護のスケジュールがすべて崩れてしまうこともあります。
車椅子移動が不可能になるリスク
私たちは高層マンションの上層階に暮らしています。普段は、玄関から外出するにも、訪問介護や訪問診療を受けるにも、必ずエレベーターを使います。車椅子の夫にとって、階段での移動はまったく現実的ではありません。
そんな生活の中で、困るのが「エレベーターの点検日」です。私たちのマンションでは点検が毎月のようにあり、ときには部品交換などで長時間止まることもあります。
数時間とはいえ、停止時間が訪問介護や訪問診療、デイサービスの送迎と重なると、大きな影響が出る可能性があります。
掲示板チェックと早めの連絡がカギ
点検の案内は事前に掲示されますが、見落としてしまったり、予定の変更が難しいこともあります。「どうやって対応しよう…」と不安になる場面も少なくありません。
幸い、これまで送り出しができなかったことはありませんが、デイサービスの送迎時間を早めてもらったり、少し遅らせてもらうなど、介護事業所の方々に相談しながら調整をしてきました。皆さんが事情を理解してくださり、柔軟に対応してくださるおかげで、何度も助けられています。
掲示板に点検のお知らせを見つけたら、すぐにスケジュール帳と照らし合わせて、必要に応じて早めに連絡を入れるようにしています。
デイサービスから突然の呼び出し|オートロックが壁になる日も

体調不良による早退で、デイサービスから急に呼び出されることは実際によくあることです。
そんなとき、迎え入れる側も急いで準備を整える必要があり、想像以上に慌ただしく気をつかう場面です。
外出中の急な要請に慌てた経験
ある夏の日、デイサービス先から突然の電話がかかってきました。
「ご主人が少し熱っぽいので、早めにお迎えをお願いできますか?」とのこと。
私は外出中で、すぐに帰宅の準備をしましたが、交通の混雑もあって、どうしても時間がかかってしまい、思ったよりも到着が遅れてしまいました。
その結果、体調が優れない夫と、付き添ってくださったデイサービスの職員の方が、マンションのエントランスで待つことに…。
オートロックの解除が間に合わず、夏の蒸し暑い中でしばらく待たせてしまったことが、本当に申し訳なくて悔しくて、今でも胸が痛みます。
「すぐに帰れる体制」を整える意識を
普段は当たり前のように通れていたオートロックも、こうした場面では「ハードルの高い壁」のように感じられました。
この出来事をきっかけに、「デイサービスに預けているから安心」とは思わず、いつでも連絡が取れるよう、外出先でも電話にすぐ対応できる体制を意識するようになりました。
たとえば、外出中もスマートフォンをすぐ手に取れる場所に置いておいたり、移動手段に余裕をもたせておいたりと、「いざというときにすぐ帰れるかどうか」を常に意識するようになりました。
それは気を張る日々でもありましたが、急な呼び出しに備えることも、在宅介護を続けていくための大切な準備のひとつだったと今では思います。
停電で介護リフトが動かない|電動機器の落とし穴
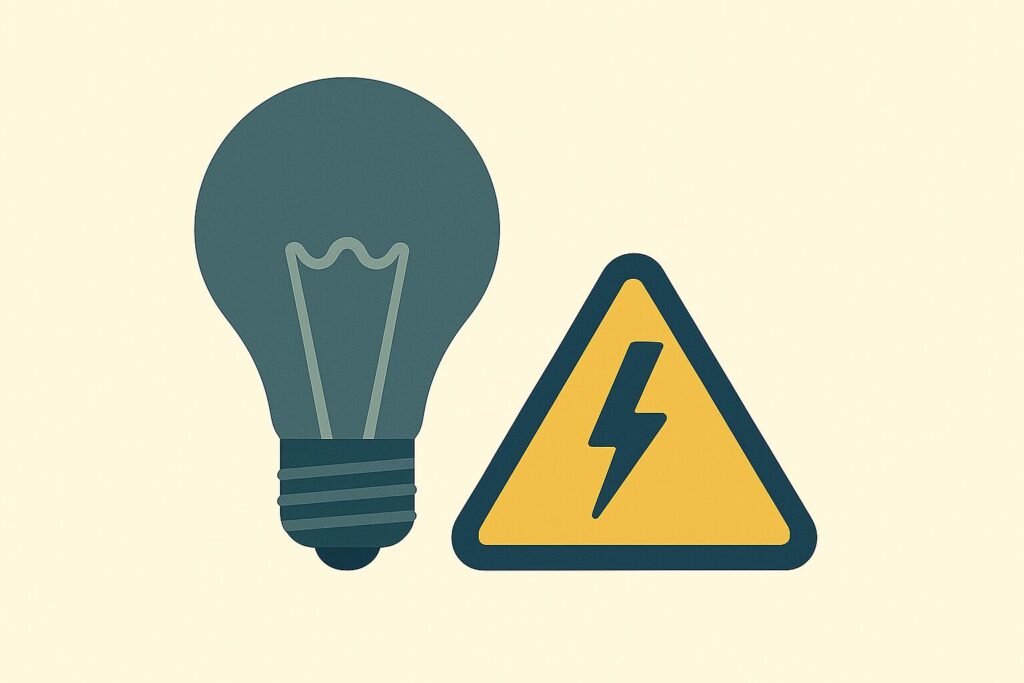
介護を少しでも楽に、そして安全に行うために導入されている電動機器。とても頼りになる存在ですが、「電気が止まったらどうなるのか?」という視点は、実際にその場面になってみないと気づきにくいものでした。
突然の停電で機器がフリーズ
在宅介護中、我が家では電動リフトを使って夫の移動をサポートしていました。また、寝ている時間が長いため、体への負担を減らすために介護用のウォーターベッドも取り入れていました。
でもあるとき、短時間の停電が起こり、「リフトもベッドも動かない」という事実に直面しました。
もし使用中に長時間停電してしまったら…? 特にリフトに乗っている途中や、ベッドが座位の状態のままだった場合、どうやって対応すればいいのか――そう思うと不安が一気に押し寄せました。
業者に聞いた「手動操作」の重要性
停電に備えて、リフトや介護用ベッドの業者さんに緊急時の対応方法を事前に教えていただく機会がありました。
教わった内容は、たとえば以下のようなことです。
- ベッドを手動でフラットな状態に戻す方法(座位で停電したときの対応)
- ベッド裏側の金具を外す場所と手順
- 電動リフトの手動操作レバーの位置や使い方などを確認
いざというとき、「道具がある」だけでは不十分で、「どう動かすか」を知っているかどうかで対応力が大きく変わるのだと実感しました。
さらに実際に手を動かしてみることで、「これなら、もしものときも何とかなるかもしれない」と、少しだけ気持ちの余裕も生まれました。
停電はいつ起こるかわかりませんが、それでも「あのとき教わっておいて本当によかった」と思える瞬間がきっとある。
そんなふうに、“知っておいて損はないこと”を少しずつ積み重ねていくことが、在宅介護における安心や心の支えにつながっていくのだと感じています。
災害時にどう避難する?要介護者の現実と支援制度

在宅介護をしていると、「もし災害が起きたらどうやって避難するのか?」という不安が常につきまといます。特に高層階のマンションでは、移動そのものが大きなハードルになります。
高層階ゆえの避難困難と不安
私たちの住まいは、高層マンションの上層階。地震や台風などでエレベーターが止まってしまったら、車椅子を使っている夫と一緒に階段を降りることは現実的に不可能です。
避難どころか、自宅に閉じ込められてしまう可能性もある――そんな不安が、常に頭の片隅にありました。
我が家には、小学生の子どもが2人います。いざという時、子どもたちを連れて避難するだけでも精一杯。そこに、夫を連れて4人でどうやって動けるのか…。想像すればするほど、胸がぎゅっと苦しくなる思いでした。
「避難行動要支援者支援制度」への登録を相談
そこで私たちは、市役所に相談し、「避難行動要支援者支援制度」への登録を行いました。
この制度は、「災害時に支援が必要な人がこの地域に住んでいます」と、あらかじめ自治体に伝えておくものです。いざというとき、自治体や地域の支援者が手を差し伸べやすくなるよう、情報を共有する仕組みになっています。
もちろん、登録すれば必ず誰かが助けに来てくれるとは限りませんが、それでも「私たち家族の存在を知ってもらえている」という安心感は、大きな支えになります。
▼制度の詳細はこちら
避難行動要支援者名簿に関する条例(一般財団法人 地方自治研究機構)
この制度の登録や相談は、お住まいの市役所で受け付けています。
もし不安を感じている方がいらっしゃれば、早めに一度、市役所へ問い合わせてみることをおすすめします。
まとめ:在宅介護に「絶対の安心」はないからこそ、備えの積み重ねを

在宅介護では、水道・電気・設備など、日常生活の小さなトラブルが、大きな支障やストレスにつながることがあります。
今回ご紹介した4つのトラブル――
- 訪問サービスの日に重なった断水
- 点検中のエレベーター停止で介護不能に
- デイサービスから急な呼び出し対応の難しさ
- 停電で介護リフトが使えないリスク
どれも、完璧に防ぐことは難しいものばかりです。
それでも、「もし起きたらどうするか」を日頃から考えておくこと、そして「家族や関係者と共有しておくこと」が、いざというときの心の支えになります。
特に、私が在宅介護のなかで強く実感した備えは次の3つです。
- 一人で抱えこまないこと
- 緊急時に連絡・相談できる相手を決めておくこと
- 小さな異変や気づきを見逃さず、声に出すこと
「何かあっても、きっと対応できる」という心構えこそが、
日々の介護に安心感と前向きさをもたらしてくれると、私は感じています。


