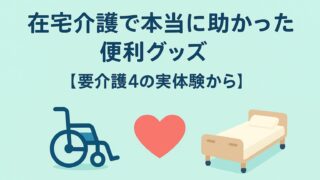維持期リハビリと在宅介護の現実|デイサービス・訪問診療・費用の悩みと家族の支え
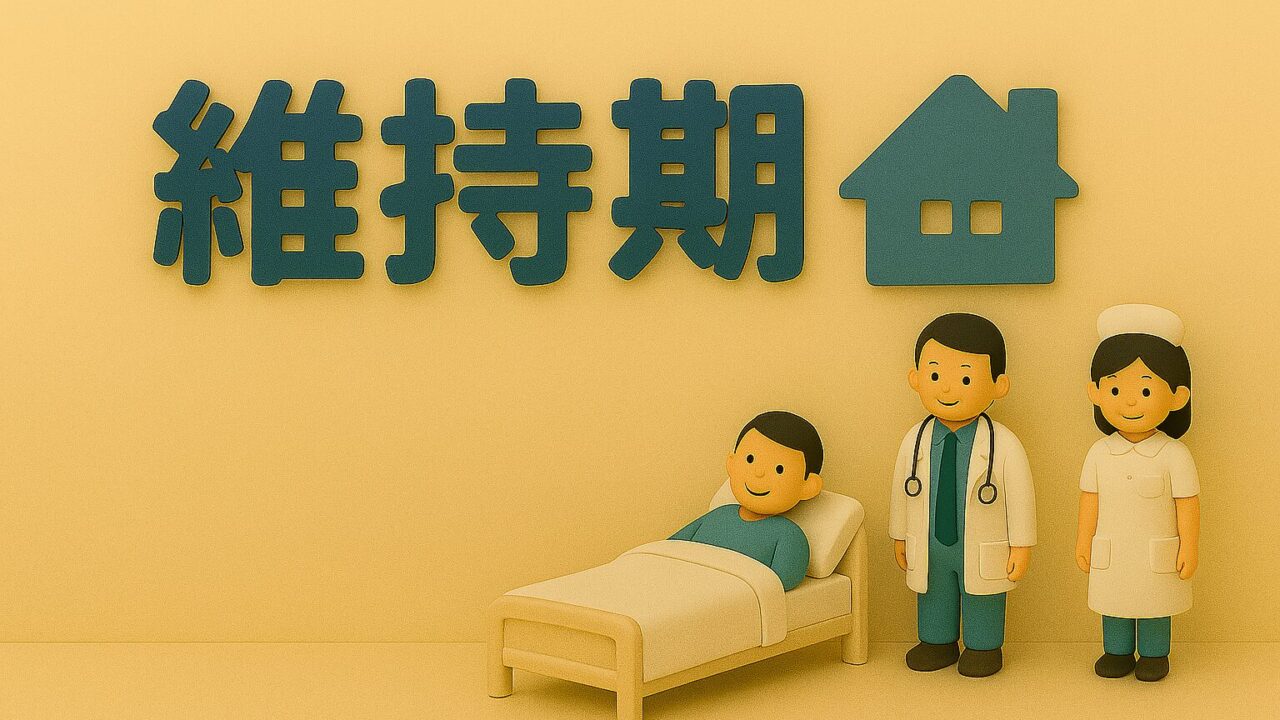
回復期病院でのリハビリを終え、自宅に戻ると始まるのが「維持期」の在宅介護です。
デイサービスや訪問診療・訪問看護など、チームでの支援を受けながら過ごす日々は心強い一方で、費用や体力的な負担を実感することもありました。
この記事では、在宅介護の流れやサポート体制、費用の現実、レスパイト入院での体験、そして家族としての気づきをまとめています。同じように維持期を迎える方の参考になれば幸いです。
維持期リハビリとは?回復期との違い
回復期リハビリでは「できることを取り戻す」ことが大きな目標でしたが、維持期に入ると「今できることを続ける」「生活を支える仕組みを整える」ことに重点が置かれます。
自宅での生活に切り替わることで、介護を担う家族の役割が増えます。大変な面もありますが、「日常の中で家族と一緒に過ごせる時間」が増えるという大きなメリットもありました。
在宅介護を支えるチーム体制
自宅に戻った私たちを支えてくれたのは、多職種が関わる在宅介護のチームでした。
デイサービス:週数回の利用で、日常生活のリズムを整えたり、家族が自分の時間を持てる貴重な機会となりました。体調に応じて柔軟に対応してもらえる安心感もありました。
訪問診療・訪問歯科:医師や歯科医師が定期的に自宅へ来て診てくださることで、外出が難しい状況でも必要な医療を受けられる心強さがありました。
訪問看護・訪問リハ・訪問薬剤:清拭や着替え、リハビリ、薬の管理など幅広くサポートしていただき、日々の介護を一人で抱え込まずに済んだのは本当に助かりました。
ケアマネジャー:サービス全体を調整してくださり、担当者会議には多くの関係者が集まりました。「こんなにも多くの人が支えてくれている」と実感し、心強い気持ちになりました。
在宅介護は家族だけでは難しいこともありますが、こうした支援があるからこそ続けられるのだと感じました。
在宅介護にかかる費用と補助制度
身体障害者手帳が交付されるまでの間は医療費助成を受けられず、在宅介護の費用は思った以上にかかりました。高額療養費制度を活用して都度申請をしましたが、支払いを続ける日々は大きな負担でした。
また、日々欠かせない消耗品も多く、まとめ買いをしながら出費を管理していました。たとえば
- おむつ、尿パッド
- 使い捨ての介護用防水シーツ、おしり拭き
- 口腔ケアスポンジ、口腔用ジェルなど
これらはすべて常備しておく必要があり、薬局でまとめて購入していました。
大人用おむつは、6ヵ月以上寝たきりで医師が必要と認めた場合に「医療費控除」の対象になります。初年度は医師の「おむつ使用証明書」で申告が可能です。詳しくは自治体や税務署にご相談ください。
そして、身体障害者手帳取得後には、特別障害者手当(月額約29,590円/令和7年4月現在)を申請しました。
申請には医師の診断書が必要で審査にも時間を要しましたが、受給できたことで助かる場面が多くありました。ぜひ活用を検討されることをおすすめします。
在宅介護で申請できる主な制度
| 制度 | ポイント |
|---|---|
| 高額療養費 | 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた分が払い戻される |
| 医療費控除 | 年間10万円超の医療費が対象。大人用おむつも条件を満たせば控除可 |
| 特別障害者手当 | 在宅で重度障害がある20歳以上に支給。月額29,590円(令和7年4月現在) |
レスパイト入院での体験
数日のレスパイト入院を利用しましたが、思っていた以上に「過ごし方」が限られていると感じることもありました。体位変換の頻度やベッドの種類によっては、褥瘡(じょくそう)のリスクもあることを実感しました。
在宅に戻ってからは軟膏を塗ってケアを続け、1か月ほどで落ち着きました。介護ベッドやマットレスの選択が、本人の生活の質や体調に大きく影響することを学んだ経験でした。
在宅介護の1日の流れ
在宅介護の1日は、まず投薬の準備から始まるのが基本でした。
朝食
- 食前薬 → 食前水
- 栄養剤投与(約2時間)
- 食後薬 → 吸引 → オムツ交換
- 顔の清拭・口腔スポンジでの口腔ケア・髭剃り・着替え
昼食
- 食前薬 → 食前水
- 栄養剤投与(約2時間)
- 食後薬 → 吸引 → オムツ交換
夕食
- 食前薬 → 食前水
- 栄養剤投与(約2時間)
- 食後薬 → 吸引 → オムツ交換
就寝前
- 眠剤の投与
- オムツ交換
このほかにも、必要に応じて1日4〜5回のオムツ交換と、食前・食後の吸引が欠かせませんでした。
また、訪問リハビリで教わった腕から手指にかけてのマッサージを取り入れるなど、日常の中で少しでも快適に過ごせる工夫を続けていました。
訪問診療や訪問リハビリの予定も加わるため、1日を通してスケジュールはぎっしりと詰まっていました。
夫は寝返りも打てないため、体位交換の工夫として電動ウォーターベッドをレンタル。在宅介護中は新たな褥瘡もできず、比較的快適に過ごせていたと思います。
在宅介護で感じたこと
大変な日々の連続ではありましたが、在宅介護には良かったこともあります。
- 夫の顔をいつでも見られる安心感
- 子どもたちが制限なく父親と触れ合える時間
- 介護を通じて少しずつ身についたスキル
体力的にも精神的にも負担はありましたが、それ以上に「家族と過ごせる時間の大切さ」を実感できたのは、在宅介護ならではの経験でした。
まとめ|支えてくれる人と制度を上手に活用しながら在宅介護を続ける
維持期の在宅介護は、家族だけで抱えるには大きな負担があります。だからこそ、デイサービスや訪問診療といった専門職のサポートや、高額療養費制度などの公的制度を積極的に利用することが欠かせません。
在宅介護は大変さと同時に、家族と過ごせる時間の価値や、介護を通じて得られる学びといったかけがえのない経験も与えてくれます。
無理をせず制度やサービスを取り入れ、支えてくれる人の力を借りながら続けることが、維持期を乗り越える大切なポイントです。
そして、負担を感じたときには一人で抱え込まず、市役所やケアマネジャーなど専門職に早めに相談することをおすすめします。
あわせて読みたい関連記事