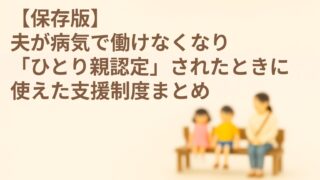心筋梗塞の回復期リハビリで家族ができたこと|入院中の工夫と在宅介護への備え

心筋梗塞の治療後、夫は急性期病院から回復期リハビリ病院へと転院しました。
私にとっては「ここからが本当の意味でのスタートだった」と、今では感じています。
けれど、実際に始まったのは、予想以上に長く、思い通りにいかない現実との向き合いでした。それでも、家族としてできたことや、小さな工夫の積み重ねが、支えとなったように思います。
この記事では、当時の経験をもとに、同じような状況にある方へ向けてお伝えしたい「家族ができたこと」「備えてよかったこと」をまとめました。
面会制限中に家族ができたコミュニケーションの工夫
回復期病院では、感染症対策の影響で直接の面会が制限されていました。ほとんどの日々をオンラインでのリモート面会に頼る生活。表情や声を確認できることはありがたかった反面、触れられない距離に寂しさもありました。
ある日、スタッフの方の配慮で、短時間の「窓越し面会」を実現してもらえたことがありました。声が届かないため、携帯電話を2台使って会話を試み、子どもたちが手を振ったり話しかけたりする姿に、夫の表情も柔らかくなったのを覚えています。
直接触れ合えなくても、つながっている実感を工夫しながら作り出すことは、回復への小さな力になっていたと思います。
食べる力の喪失とリハビリのもどかしさ
急性期では口からゼリーやお水を摂れていたのに、回復期では胃ろうだけの生活に変わり、経口摂取が一時中止になりました。
その結果、飲み込む力が著しく低下し、ST(言語聴覚士)さんからは「再び口から食べるのは難しいかもしれません」と伝えられました。
PT(理学療法士)さんやOT(作業療法士)さんによるリハビリは毎日ありましたが、筋力や柔軟性の低下は避けがたく、時間が経つにつれて、足首が床につかなくなり、体は硬くなっていきました。
体が変わっていく現実に直面しながら、家族として何もできない悔しさと向き合う日々が続きました。
「声を出す」「うなずく」──小さな変化を見逃さず喜ぶこと
入院から1ヶ月ほど経ったある日、歩行訓練の際に夫がかすかに声を出したことを、担当のPT(理学療法士)さんから教えていただきました。
「歩くことと、声を出すことはつながっているんですよ」と聞き、もしかするとこのまま話し始めてくれるかもしれない──そんな期待がよぎりました。
けれど、その後 声を出すことはありませんでした。
それでも、急性期には首がぐったりと下がり、ひとりで頭を支えることすら難しかった夫が、回復期に入ってからは、うなずきや首振りで意思表示ができるようになりました。
「はい」「いいえ」を表現できるようになったことは、コミュニケーションの第一歩として大きな前進でした。
しかも、私たち家族だけでなく、リハビリスタッフや看護師さんなど、家族以外の方に対しても反応を示せるようになったことは、本人にとっても大きな意味があったはずです。
食べる力は失われてしまいましたが、「伝える力」が少しずつ育まれていく姿を見られたことは、回復期リハビリならではの希望だったと思います。
それは、本人の努力はもちろんのこと、毎日関わってくださった医療・リハビリスタッフのみなさんの力によるものでした。
回復期入院中にできた家族のサポートと制度の準備
回復期の長期入院中、家族として実際に取り組めたことがいくつかありました。それは、退院後の生活に向けた制度の準備と手続きです。
- 障害年金の診断書依頼と申請スケジュールの調整
- 身体障害者手帳の取得準備
特に障害年金の申請は、傷病手当金の支給が1年6ヶ月で終了する前に備える必要がありました。退職の時期とも重なり、収入が途絶えることへの不安が大きく、経済的な支えとしてとても重要な制度でした。診断書の作成には時間がかかることが多いため、早めに依頼しておくことが安心につながりました。
また、身体障害者手帳の取得も、在宅介護で重度訪問介護をを利用するために必要なものでした。結果的に介護保険が優先となり重度訪問介護の利用には至りませんでしたが、この手帳があることで、後に夫の病気による「ひとり親認定」へとつながり、子育てや生活支援の面でも助けられました。
障害年金と健康保険組合の「傷病手当金」が一時的に重複し、支給調整や返金手続きが必要になる場面もありましたが、長期入院による医療費の支払いには大変役立ちました。経済的な不安を軽減できたことで、家族としての精神的な余裕にもつながったように思います。
退院に向けた希望と、在宅介護への心構え
退院が近づくと、PT・OTのスタッフの方が夫と一緒に自宅を訪問し、介護環境の確認をしてくださいました。手すりの位置、ベッドの配置など、細やかな点までアドバイスをいただきました。
その日は夫にとって数か月ぶりの自宅訪問で、嬉しさのあまり涙を流していました。
実際に夫を車椅子に乗せた状態で、自宅(マンション)のエントランスから玄関、室内の段差や車椅子での動線などを一通り確認しました。
その体験を通じて、退院後の日常生活でどこに負担がかかるのか、介助する側としてどの場面で工夫や支援が必要かが明確になりました。実際に動いてみることで初めて気づくことも多く、在宅介護を視野に入れるうえでとても大切な準備だったと感じています。
私たち家族も「もう一度この家で一緒に暮らせるかもしれない」という希望を持つことができました。
ただ、在宅介護は決して簡単ではありません。 レスパイト入院先で褥瘡ができるなどのトラブルも経験し、体調の管理と医療体制の重要性をあらためて感じました。
まとめ|回復期リハビリを支える家族の役割
回復期の入院生活は、決して「元気を取り戻していく穏やかな時間」ではありませんでした。
- 面会制限の中でも「つながる工夫」をすること
- 身体機能の維持に向き合い、できることを一緒に続けていくこと
- 制度準備や住環境の整備など、家族にしかできない支えがあること
- 医療やリハビリのスタッフと連携し、小さな回復の兆しを見逃さず共に喜ぶこと
「声を出す」「うなずく」といった変化を見逃さず、回復を信じて支え続けた日々が、少しずつ希望をつないでくれたように感じました。
この体験が、今まさに回復期を支えているご家族のヒントになれば幸いです。
▶次の記事:【維持期(在宅介護)】へ続く予定です。